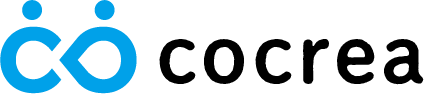過去の質問一覧(すべて)
リモートワークの案件を紹介するインターネット広告経由で、お仕事を始めました。実在するグローバル企業の案件でしっかりしたシステムだったため、安心して仕事を始めました。仕事をするのにシステム利用料が必要となり、決まったユニット(数)の仕事を終わらせば、システム利用料は仕事の報酬とともに振り込まれる形です。手数料が無料だとWebサイトには記載していたのですが、実際にはシステム利用料やその他の手数料が高額です。規定のユニットの仕事を完了したので、引き出し依頼をしたのですが、その会社はのらりくらりと言い訳をしそして
管理手数料や税金などを私が支払わないとお金が引き出せないと言っています。アカウントやドメインをしっかりと確認したところ、なりすましの可能性が非常に強いです。お金を取り戻したいのですが、どのような手続きを行えばよいでしょうか。インターネットに明るく、自分は騙されないと思っていましたが、かなり巧妙な手口です。どうぞよろしくお願いいたします。
コピーライター向けのオウンドメディアを運営しています。
1.私がおすすめのコピーライターの「求人情報」をスプレッドシートにまとめ、サイトのコンテンツとして掲載したいのですが、これは職業斡旋に抵触してしまうでしょうか?(職業斡旋には免許が必要だと聞きました)
2.企業から直接ご連絡をいただいて掲載することはありますが、その際にお金をもらうことはありません。
純粋にサイト訪問者さんが、求人情報を見つけられるお手伝いをしたいのですが、どのような行為をしてしまうと法律に抵触してしまうのかぜひご教示願いたいです。
ソフトウェア開発をフリーランスで行なっています。
委託者から送られてきた業務委託基本契約書では、契約不適合責任内容があるので請負契約だと思っていましたが、契約書とは別に日当金額を提示されています。出張などはありません。通常の開発業務を日当でということになります。
ソフトウェア開発の場合、請負契約は納品に責任がありますので、日当に関わらず見積もり金額等で契約をするのが基本と思っていましたが、日当が発生することで準委任契約とどう違うのでしょうか?
もし、日当での報酬であることから準委任契約が望ましい場合、基本契約書を変更してもらうよう委託者に連絡しようと思っています。
請負で、ある会社で個人事業主として働いています。そのある会社(国の機関)で求人を出していて、採用の条件の中で、前に雇用されていた場合、退職から2年間隔を空けなくてはいけないと記載がありました。しかし、明らかに退職してから1年ほどしか空いてない人が採用されました。これは法律的な部分で違反にはならないのでしょうか。
... もっと見る【利用規約の作成について】
現在、飲食店を経営しているのですが、その店舗を使ってシェアキッチン・シェアスペースを始めたいと考えております。それに際し利用規約を作成しており、主に下記の内容を盛り込んでいるのですが、過不足ないかをご確認いただきたいです。
・利用スペース使用後は、機械設備ふくめ使用前と変わらない状態にする
・利用日時は相談のうえ取り決め、実行される
・食中毒や盗難、故障等のトラブルが発生した場合は借主の責任となる
・キャンセル料金規定
・PL保険の各自加入を求める
※私が住んでいる地域の保健所の規則的には、一つの営業所で一人の衛生管理責任者という扱いになり、食中毒等が発生した場合は私の責務になるとのことでした。そのため、利用規約にてしっかり民事の取り決めを交わす形にしたいと考えております。
確定申告に関する質問です。準委任契約による委託業務の月単位の報酬は、請求書を発行した時点で売掛扱いとして事業所得に計上してもよいのでしょうか?あるいは、入金があるまで事業所得には計上できないのでしょうか?
当方、昨年の途中で退職し、フリーランスとなり、初めての確定申告のため、12月分の報酬(12月末に請求し、1月に入金されたもの)を前年分に計上してよいものか思案しているところで、前年分に計上できるならその方が好都合という状況です。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
個人事業主でWEBライターをしています。
確定申告の際の経費について質問です。以下のものは経費に含めても良いでしょうか。
・仕事中PCを使用する際に使用する手首のサポーター
・仕事中に使用するために購入した軽量めがね
・仕事中に使用する眼鏡につける鼻パッド
これらは基本的に仕事用に購入したものなので、日常生活で使うことはなく仕事中にしか使用しておりません。
細かい質問となってしまい、大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
医療費控除が過去5年分さかのぼって申告できると拝見しましたが
令和3年分の医療費控除を改めてする場合、控除されるのは令和3年度の所得税ですか?令和4年分の所得税ですか?
よろしくお願いします
サブスク集金に利用している決済代行会社から「インボイス制度には対応しない」旨の連絡がありました。(※毎月の適格請求書発行事業者の登録番号入りの請求書や領収書の発行機能は設けず、メールでカード決済が完了した通知のみ行うとのこと。)
このような場合、サブスク登録時に適格請求書発行事業者の登録番号入りの契約書を巻くことになると思いますが、私自身、これまでサブスクサービス登録時に、電子契約書にサインするなどは行ったことはありません。カードを登録してすぐにスタートできることが殆どです。
どのように対応するべきなのでしょうか?
Webライターをしている者です。
秘密保持契約(NDA)について質問させていただきます。
業務委託の形で企業から内定をもらいましたが、秘密保持契約(NDA)を結ぶよう言われました。
内容を確認すると以下の内容が記載されており、不安に感じております。
・情報漏洩があった際、賠償金は上限なしで負担
・疑いのある際は、自宅の立ち入り監査が入る
上記のような内容は、よくあるものなのでしょうか?
ライター側に負担が大きいのではないかと感じました。
秘密保持契約を結ぶか迷っております。
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
確定申告におけるエンジェル税制の優遇措置Aにおける寄付金控除について相談させてください。
1社目は1800株を306000円で、2社目は264株を198000円で合計2社のベンチャー企業の株式を新規取得しました(過去に同じ会社の株式の取得をしたことはなく2社とも今回が初めてです)。
「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」を2社分作成してみて確定申告にどの数字を使えばいいのかがわからなくなりました。
ふるさと納税もしているため寄付金控除額の正しい計算式がわからないという状態です。
以下の1か2のどちらかだと思うのですが、どちらの計算式が正しいでしょうか?
「所得から差し引かれる金額」欄の㉘「寄付金控除」 = (ふるさと納税の合計額 - 2000円) + (1社目の⑦寄付金控除額(2千円控除済みの額)) + (2社目の⑦寄付金控除額(2千円控除済みの額))
「所得から差し引かれる金額」欄の㉘「寄付金控除」 = (ふるさと納税の合計額 + 1社目の⑥2千円控除前の額 + 2社目の⑥2千円控除前の額) - 2000円
また、取得費の調整対象額についても不明なため確認したいです。
「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」の「1 寄付金控除額の計算」⑧〜⑩や「2 控除対象特定新規株式の取得費の調整対象額等の明細」も記載してみましたが、これら取得費の調整対象額は確定申告書のどこかに記載するものなのでしょうか?
長文になってしまいましたがご回答いただけますと幸いです。
各位
はじめまして。
この度は、青色確定申告の自宅の業務利用に係る経費(減価償却費)、資産計上に関してご相談させていただきたくご連絡させていただきました。
私は、自宅にてIT関連の開発業務に従事している個人事業主です。開業して5年になり、これまでは事務所を借りておりましたが、2022年の5月1日から自己所有マンション(2015年3月30日登記 35年ローン)の自宅1室を仕事部屋とし業務しております。本年の確定申告に際して業務利用部分の減価償却費を経費として計上したく考えておりますが、申告内容として下記の認識で正しいか否かをご教示いただけますと幸いでございます。
【業務使用を開始した時点の減価償却費残高の算出方法】・2022年5月1日よりの開始だが、未使用期間が6ヶ月未満のため2022年1月時点の減価償却残高と同様の計算方式でよいか。なお、計算式は、1.非業務用であった期間の減価償却累計額=(売買契約書の消費税額から建物部分の価格を算出)×0.9×0.015×62.2022年1月1日時点の減価償却費残高=建物部分価格ー1.の計算結果
【固定資産台帳への記帳】〈ご参考〉会計ソフトはマネーフォワード確定申告を使用勘定科目:建物数量または面積:1取得日:2015/03/30(登記された日)焼却方法:定額法耐用年数:47事業供用開始日:2022/05/01事業利用比率:9.89%(床面積にて算出)期首残高:上記2.で算出した2022年1月1日時点の減価償却費残高
【2022年開始時点残高】2022年1月1日時点の減価償却費残高を「建物」として記帳
【2022年期末残高】2022年1月1日時点の減価償却費残高ー(建物部分取得金額×0.022)
【経費計上】建物部分取得金額×0.022×8/12の金額に家事按分として0.0989を掛け計上
恐れ入りますが、上記内容で税法上問題ないか、何卒ご教示頂きたくお願い申し上げます
自宅として使っているマンションは居住用のため、個人事業主の事務所として登録できないと知りました。そこでバーチャルオフィスを事務所として登録し、実際に仕事をする場所は自宅(居住用マンション)や契約先事務所、シェアオフィスにする案を検討しています。
このように、事務所はバーチャルオフィスに登録し、仕事は自宅(居住用マンション)で行うのは問題ないでしょうか?
問題ない場合、自宅で使用した電気代やネット代は、案分して経費計上してもよいものでしょうか?自宅を事務所として登録していないのに経費計上してよいものか気になります。
仕事は、パソコンとネット環境があればできる業務です。
個人事業主で仕事をしています。
自宅(持ち家、親名義)で仕事をしていますが、これを家賃の支払いをして経費に計上することは可能でしょうか?
契約書を作成し、それに基づいて家賃を親に払う
自宅は離れとなっており、仕事のためにもっぱら利用する
風呂や洗濯場などが離れにあるため、完全に仕事用とはいえない(その分は契約書に明記する)
生計を一にしている親族への家賃支払いは経費として認められないようですが、上記のように契約書を作成してそれに基づいての支払いでも難しいでしょうか?
ちなみに仕事用にするために、弟が一緒に離れで生活していましたが、母屋に移動してもらっています。(仕事のために移動してもらっている)
このような条件でも税務上否認されるものなのでしょうか?
青色申告の個人事業主です
Apple公式サイトでPCを購入したら初売り特典として32000円分のギフトカードがついていたのですが、請求書としてはPCから32000円割引される代わりに別途ギフトカードの32000円が請求されました。この場合別途請求された32000円の勘定科目、会計処理方法について教えて下さい。会計ソフトはfreeeを使っています
■想定していた会計処理
PC:274,800円→備品として固定資産を登録
■Appleからの請求書
PC:242,800円(PC本体274,800円からギフトカード32,000円引かれている)→備品として固定資産登録の認識です
ギフトカード:32000円→????
個人事業主です。
2022年12月分の売り上げで、支払いが2023年1月末のものがあります。
源泉徴収がある売上なのですが2023年1月のまだ支払いがされていない時点で還付申告をする際には12月の未回収分の源泉徴収額に関しては「未納付の源泉徴収税額」の欄に記載するのでしょうか?
支払いがあってから、2023年2月に還付申告をする場合には未納付ではなく、「源泉徴収税額」の欄に記載すれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
個人事業主です。小規模事業者持続化補助金の収益計上時期について教えてください。
昨年「交付決定」した小規模事業者持続化補助金があり、事業実施後の支給金額確定は今年になります。補助金・助成金の収益計上時期は「収入すべき権利が確定した事業年度」=「支給決定時の属する事業年度」という情報を見ましたが、小規模事業者持続化補助金の事業の手引きには「補助金は会計上、支払額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり」と書かれており( https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3_js_tebiki09.pdf#page=51 )、本補助金は「交付決定」した昨年か、「支給金額が確定」する今年か、どちらで収益計上すればよいのか困っています。
お教えください。(ご回答がつかないため1月1日投稿分を再投稿いたします。すみません)
【マネーフォワードクラウド確定申告】
残高試算表および推移表を見返して気づいたのですが、普通預金欄が事業用に作った口座ではなくプライベートな口座になっていました。こちらは変更可能なのでしょうか?または、そのままにしておくと起こりうる問題はございますか?
個人事業主です。
クラウドソーシングサイトで収入を得ています。
現在行っている仕事とは別の分野の仕事もこれからやっていきたいと考えているのですが、
登録したいクラウドソーシングサイトは「アカウント数は一人ひとつまで」という決まりがあります。
そこで、青色専従者である妻の名義でもうひとつアカウントを作れないかと思うのですが、
妻名義のアカウントや銀行口座で収入を得た場合、妻が確定申告をしなければならなくなるでしょうか。
それとも私の事業収入となりますでしょうか。
妻名義のアカウントで妻も私も仕事を請け負う場合と、私のみが仕事を請け負う場合で結果が違うようでしたら、それについてもお教えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。