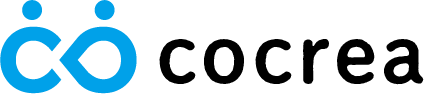過去の質問一覧(すべて)
毎年青色申告で確定申告を行っている自営業者です。
今年から、練習目的を兼ねているものの、低価格でコーチングをするようになりました。
通常の売上ですと、お客様の企業名を記帳するのですが、コーチングの場合には守秘義務があるので、クライアントの名前を記録することに問題を感じます。
freeeを使っているのですが、freeeに取引先としてクライアントの実名を記録しなくてはならないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
アフェリエイト事業で稼いでいる自ブログに貼り付けてある自分で撮影した写真が、他人ブログに無断利用されていますが、利用料を請求しても対応していただけません。このあとどのような対応をすればよいでしょうか。
... もっと見るこれからおにぎり専門店を開店したいと考えており、「女性、若者/シニア起業家支援資金」という融資制度を利用する前提で計画書を作成しています。
それにあたり、確実に融資がおりるような計画書にしたいのですが、問題がないかどうかのチェックと、アドバイスをいただけないでしょうか。
カメラマンをしておりますが、撮影した写真をプリントし台紙に貼り納品したりアルバム作成を行うことが少しずつ増えてきました。とはいっても年10件もないため支払い手数料・外注工賃・雑費などの勘定科目を使用しておりましたが、今後増えてくることを考えるともっと適切な科目にした方が良いのではと思っております。
この場合どう仕訳けたらよいでしょうか?なお、アルバムは自分でデザインし印刷のみ発注、台紙写真は写真プリント代と台紙購入があります。
【事業所得以外に給与所得を得た場合の手続きについて】
現在、個人事業主として業務委託で事業所得を得ているのですが、業務委託とは別にアルバイトで給与所得を得た場合、確定申告書の給与所得欄に記載が必要になりますが、月々の仕訳はどのように登録すれば良いのでしょうか?
(事業所得に関しては、毎月、借方:売掛金/貸方:売上高で仕訳登録しています)
お世話になります。
業務委託契約書内の記載の法的拘束力についてご質問させてください。
現在フリーランスとして業務委託契約書を締結し、仕事を行っております。
その中に本契約解除後、3年間は同様の仕事や業界に関わってはいけないという内容が盛り込まれております。
どこまでこの内容を遵守すべきかご意見をいただけますと幸いです。
法的拘束力があるのか、ないのかだけでもご回答いただけると大変助かります。
【スクリーンショットの扱い方について】
WEBライターをしている者です。紹介記事を作成する際に企業HPのファーストビューや、申し込み手順などをスクリーンショットするようにクライアントから依頼されました。※違法なダウンロードではありません引用を正しく使えばスクリーンショットは使用可能だと思うのですが、以下の内容について質問があります。
①「引用:〇〇」と「出典:〇〇」はどちらが正しいのでしょうか。②スクリーンショットを以下のようにトリミングするとのは問題なのか。→PCでスクリーンショットした際のPCのタグや時間、検索窓など不要な部分→企業HPにある広告画像やPR表示
お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
業務委託(準委任契約)で3か月ごと更新の契約を結びましたが、体調不良が続き、契約の更新をしないことを申し入れようと考えております。伝え方等、法律上のリスクとならないような注意点がありましたらアドバイスを頂けましたらと存じます。
... もっと見る個人事業主として、クライアント様と業務委託契約をし、WEB管理サポートを行っております。契約書に料金の最終確認はクライアント側にある旨、あるいは、こちらでは責任を負わない旨の記載を行っておりませんでした。今後、業務委託契約書に記載したいと思っております。どのような一文を記載するのが適当なのでしょうか。また、既に締結済みのクライアント様とは改めて契約書を交わし直すという事でよろしいでしょうか。ご教授頂けるとありがたく存します。
... もっと見る個人事業主です。
先日、クライアントと業務委託の解約をしたのですが、再契約をする運びとなりました。
解約時にメールでの合意だったのですが、今回の再契約もメールでの合意で問題ないのでしょうか。
その場合、下記の内容で差し支えないでしょうか。
「○○○○年○○月○○日をもって合意解約をした○○契約について、××××年××月××日より同条件にて再度契約を締結するものとする」
他、相互確認が必要な事項がありましたらご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
とある学校を受講しました。
その学校で教えていることは、自分では一切模倣していませんが、その担当者から「同じターゲット顧客を狙っているような表記は、規約に反する」といわれてしまい困っています。規約には、退学と書いてあるのですが、退学になっても特に影響はないのです。その後、その学校とは全く同じ理論は持ちいれていませんが、法的に訴えられるものなのでしょうか?
現在、個人事業主(コンサルタント業)ですが、事業が軌道に乗ったため、合同会社にすることを検討中です。
合同会社では、自分が出資した範囲内でのみ会社の債務について責任を負う、とされていますが、顧客との契約書において、損害賠償額の上限が定められていない場合、どちらが優先されるのでしょうか?
現在、個人事業主(コンサルタント業)として活動していますが、事業が軌道に乗ったため、合同会社にすることを検討中です。
Q1 個人事業主として青色申告する場合と、合同会社として税務申告する場合を比較して、どちらが節税となりますか?
Q1 合同会社設立の書類と個人事業主廃業届の税務署への提出は、同日である必要がありますか? それとも、一定期間両者が重複して存在しても問題ありませんか?
Q3 合同会社の設立を5月にしたいのですが、個人事業主の事業年度の途中で個人事業主を廃業しても問題ありませんか?
個人事業主でfreeeを使用しています。
freeeのカード明細連携機能を使用しています。ただし、引き落とし口座の連携はしていません。
複数カード連携している中でJR東日本系のカードの運用が特殊かと思いますので質問させていただきます。
このカードでの利用明細は基本的には個人事業用として、経費計上しています。こちらについては特に特殊な要素はありません。
ただし、このカードはモバイルsuicaと連携していて、時々、オートチャージ分の明細が発生します。
そして、こちらの分は、プライベートな費用です。
このオートチャージ分について、freeeのプライベートとして処理を選ぶと、
〇〇経費 / 事業主借
(クレカ取引の関係で、これとは、ことなる仕訳が自動生成されているかも...)
という自動仕訳が作成されるので、あとで消込は面倒とおもって、
今期の途中から、freeeの「明細は無視する」処理を行っていました。
ところが、ネットでいろいろ調べていますと、
このようなケースでは、「プライベートとして処理」をすべきとのことでした。
参考)
https://note.com/ganahacpatax/n/n9674c3a7e445
そうすると、上記の自動仕訳が生成されて、面倒化とおもっていたら、
以下の記事を発見しました。
事業主貸と事業主借に『返す』はない・決算でも何もしない
https://useacc.com/2018/07/23/jigyounushigashi-kaesu/
== ここまで状況と前提説明、以下から質問 ==
1)去年の運用では、オートチャージ分について「プライベートで処理」をしていたので、
確定申告書で、貸借対照表に、事業主貸、事業主借に残高が計上されていますが、
こちらは特に消し込む必要なしとの考えで問題ないのでしょうか?
2)今季は、オートチャージ分について「プライベートで処理」していた時期と、「明細を無視」していた時期が混在してます。これについてはさかのぼって、取引を修正し、すべて、オートチャージ分について「プライベートで処理」で統一というのが正解なのでしょうか?
※市販のフリーランス経理処理等の書籍をみましたが、クレカや銀行口座との自動連携を踏まえた、事業主貸借に関連する体系的な説明を見つけることができなかったので、この場で質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
このたび合同会社を設立しました。これまで個人事業主としてidecoを上限いっぱい掛金拠出していました。
法人化にともない、idecoに次の手続きをしようと思いますが、どの順番で行うのがよいでしょうか。
また、手続きの過不足がありましたらご指摘いただけると幸いです。
1.加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)k-101b
2.事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 k-101a
3.idecoプラスに関わる届け出書類
(中小事業主掛金納付開始・終了届 (K-301)
中小事業主掛金対象者登録届 (K-303)
中小事業主の資格に関する現況について 省令様式第10号(K-307)
中小事業主掛金を拠出すること及び中小事業主掛金の額の決定に関する同意書 省令様式第11号(K-308)
中小事業主掛金納付事業所登録申請書(事前登録用)(K-314)
預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書(K-007B) )
年度内に会社を退職して個人事業主になるにあたり、ご相談させていただきます。
①健康保険について、任意継続か国保かを検討中です。現職と役所に保険料を確認して、任意継続の方が月額保険料が安いことがわかりました。ただ、一般的に独身で扶養なしの場合は国保の方が安くなるというお話をよく聞きますが、任意継続の方が安くなるパターンはよくありますか?年収は500-550万程です。今年度は保険料が安い方に加入し、来年度はまた役所に問い合わせして、どちらに加入するか検討する形がベストでしょうか。
②年金について。個人事業主になるため、国民年金に加入者することになるかと思います。企業型DCに加入して積み上げた分は、65歳以降に受取の申請を自身で行う必要がありますか?
今後、1階建ての国民年金以外を考えた場合、iDeCoやNISAに自身で入ることになるということであってますでしょうか。
③会社の持株にも加入しているのですが、こちらは一般的に退社後、現金受け取り、証券口座開設して運用、どちらが有利に働きますでしょうか。
多くの質問失礼しました。何卒よろしくお願いいまします。
現在、個人事業主として働いています。(年間売上1200万円程度)
社会保険料の節約のために、以下のようなことが可能か検討していますが、違法性はありますでしょうか。
①資本金100万円にて株式会社を設立。(100%私自身が出資)②設立した会社の代表取締役に私自身が就任。社員は私のみ。役員報酬は月5万円程度とする。③私自身は会社の社会保険(健康保険・年金)に加入する。④設立した会社は実態として事業は行わず、売上は計上しない。(役員報酬、社会保険料、住民税などの最低限の支出のみを行い、毎年赤字となる。資本が尽きそうになったら、私自身で新たに出資する)
こんにちは。個人事業主で企業と業務委託契約を締結しています。
この度、こちらの都合(事業廃業)にあたり契約を解約することとなり、先方からも同意を頂きました。
この場合、「合意解約」「合意解除」どちらの表現が正しいのでしょうか。
また、正式な書面でなく、メール等での相互確認でも解約(解除)は成り立つのでしょうか。
宜しくお願い致します。
お世話になっております。
このたび新居を購入し、今年の9月より35年ローンにて返済を開始します。
フリーランスのため、新事務所購入費用として一部を青色申告に計上しようと思うのですが、
どのように記帳したらいいかわからないため、質問させていただきます。
使用ソフトは「やよいの青色申告」クラウド版です。
夫と折半してローンの返済と固定資産税を支払う予定です。
以下のような認識でいいのかご教示いただきたいです。
1)土地、建物費用の(約5000万)を按分し、固定資産として登録
2)3か月ごと?に来る固定資産税の支払いを按分し、別途記帳
お手数ですがご確認のほど、よろしくお願いいたします。